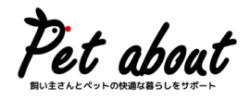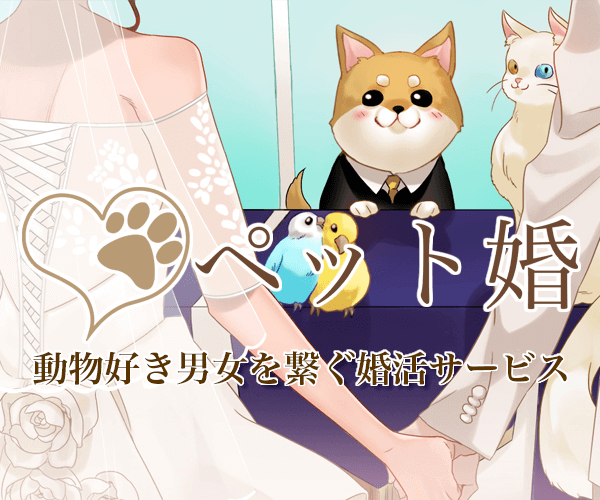飼っているうさぎが、
よく下痢をする
食欲がない
歩き方がおかしい
などという症状が確認されたことなどはありませんか?
もしそれらの症状が確認できたら、何かしらの病気のサインかもしれません。
今回は、ロップイヤーを8年飼育していた私、てぃもひこが、自身の経験をもとに、うさぎがよくかかる病気の症状や予防法などについて解説していきます。
どのような原因で病気にかかり、正しい治療法を知っておくことで、焦らずに対応することができます。
それでは、ひとつひとつ見ていきましょう!
うさぎはデリケートな動物
うさぎを飼うにあたって知っておかなければならないことは、うさぎはとてもデリケートな動物だということです。
古くからうさぎは捕食される生き物であり、絶えず五感をフル活用し、周囲を伺いながら生き延びてきました。
現代のうさぎもその非常に憶病で用心深い性格を受け継いでいます。
そのため、あらゆることに敏感で日常のちょっとしたことでもストレスを感じてしまい、それが様々な病気の引き金になることもあります。
他にもちょっとしたことでケガをしてしまったり、ご飯を全く食べなくなってしまったりすることもあります。
普段と少し様子が違うなと思ったら周りにストレス要因がないか今一度確認してみましょう。
もしかしたら飼育の仕方にも問題がある可能性もあります。
うさぎは与える食事の量や運動だけではなく、ケージの場所や部屋の気温などでもストレスを感じて体調不良をおこすことがあります。
周囲の騒音や匂いなどにもとても敏感です。
うさぎは繊細でデリケートな動物であるということをしっかりと理解し、普段の生活の中でウサギの心身の健康を維持していくことが飼い主として大切な役目だと言えるでしょう。
うさぎによくある病気一覧
うさぎによくある病気・症状を以下にまとめました。
比較的治療が難しくないものや対策が日常的にできるもの(よくある病気・症状)と、
手術などの大掛かりな治療を要し、うさぎの生命に関わる病気(重篤な病気・症状)
に分けて解説していきます。
毛球症
消化管うっ滞
下痢
脱毛・皮膚病
パスツレラ感染症
熱中症
歩行異常
尿石症
糖尿病
不正咬合
うさぎの歯は切歯と臼歯合わせて28本もの歯があるのですが、人間と異なり、うさぎのそれは一生伸び続けていくものです。
通常は牧草やある程度硬い食べ物をかみ砕くことによって歯が摩耗して削られていくのですが、柔らかいおやつやペレットばかり与えていたり、牧草をあまり食べなくなっていたりすると歯が刺激を受けずに伸びっぱなしになってしまい、結果的にかみ合わせが悪くなってしまうことがあります。
これを「不正咬合」といいます。
放置すると病気になってしまうこともありますので、なるべく早めに対処しましょう。
予防法としてはやはりペレットやおやつばかりではなく牧草を中心に食べさせることです。
また、ケージの柵を咬んで歯にダメージを与える行為なども不正咬合に繋がるので、しっかりとしつけてやめさせることが重要です。
毛球症
うさぎは体を舐めたり抜け毛がついているエサを飲み込んでしまったりすることがありますが、その飲み込んだ抜け毛が糞と一緒に排出されず、体内に溜まってしまった結果、胃腸の機能が著しく低下する病気を「毛球症」と呼びます。
これにかかると食欲低下、体重減少、またお腹の張りなど身体の不調がみられ、水をよく飲むようになります。
また、毛を飲み込んでしまったとしてもできるだけスムーズに排出されるよう、高繊維質のティモシーを与えたり運動をさせたりして腸内環境を良好にしてください。
消化管うっ滞
上の毛球症と異なり毛を飲み込んだことで起こるものではなく、他の原因で胃腸のはたらきが低下するのは「消化管うっ滞」と呼びます。
食べたものが胃腸に溜まってお腹が痛くなる、またその影響でご飯も水分も摂らなくなることから排出が減少するなどの症状が現れます。
重い症状だとうずくまって動かなくなることも…
主にストレスや病気などが原因とされています。
季節の変わり目や急激な温度変化などに注意しましょう。
また突然の多頭飼いや他のお動物と一緒の部屋で飼育するのはなるべく避けてください。
大きなストレス源になる可能性があります。
気温や湿度の変化で体調を崩した場合もうっ滞にかかりやすいため、寒い時などは出来るだけ体を温めたり、可能ならばマッサージなどもしてあげましょう。
お水はいつでも飲めるようにしておくことも忘れずに。
キャベツなどはお腹にガスが溜まりやすいので控え、食事はお腹にやさしい高繊維質のティモシー(牧草が中心でペレットは補助食)を与えてください。
下痢
環境の変化、食べ物、また感染症でかかることが多いといわれます。
特に仔うさぎは家に迎えたときなどに、慣れないストレスから軟便になってしまいがちです。
食事の急激な変化も消化不良を起こすことがありますので、新しいものを与える際には少量ずつにしましょう。
寄生虫や細菌などの感染で起こる下痢は特に注意が必要です。
仔うさぎや高齢のうさぎがかかってしまうと、その免疫力の弱さから生命に関わる危険性が有ります。
特に仔うさぎは食べ物を突然変えたり強く抱きかかえたりしないようにしてください。
飼い主のこうした行為で下痢をはじめとする体調不良を起こすことがあります。
また、飼育ケージの衛生状態が良くないと寄生虫や細菌の温床となってしまいます。
感染症の下痢にかからないよう飼育スペースは定期的に掃除をして清潔に保ちましょう。
脱毛・皮膚病
うさぎは犬や猫と異なり肉球が無く、身体のほとんどが毛でおおわれています。
そのためか、一度毛が抜けて皮膚が弱って炎症を起こしてしまうと治るのに時間を要します。
最悪放置すると膿瘍になってしまう可能性もあるので似たような症状を見かけた場合はなるべく早めに専門医に相談することをおすすめします。
床の材質が硬く、足裏への衝撃が強いとその部分の毛が抜け落ちてしまうことがあります。
床の材質はなるべく柔らかいものを使いましょう。
スタンピングの回数が多いウサギも注意が必要です。
また足元が糞尿などで不衛生だと皮膚に細菌感染を起こす危険もありますので、必ず足元は清潔な状態を保持するようにしてください。
皮膚の炎症に関しては、環境だけではなくうさぎ自体に炎症を起こしやすい体質がある可能性もあるため、飼う前にウサギの体質を調べるのも1つの手です。
パスツレラ感染症
気温の変化が激しい、不衛生な環境、もしくは寒い場所での飼育が原因で起こる細菌感染の呼吸器系の病気です。
うさぎは鼻で呼吸をしますが、これが原因で鼻炎(スナッフル)になってしまい、呼吸音に異音が混じります。
またストレスを過度に与えないことも重要です。
熱中症
人間と同じくウサギも熱中症にかかります。
ぐったりして動かなくなり、30℃以上の高温が続くと死んでしまうこともあります。
ウサギを飼う場合、特に夏場と気温の変化の激しい季節は注意する必要があります。
うさぎは人間のように発汗で体温調節ができないため、熱中症にかかってもなかなか分かりにくいですが、食欲が無かったりグッタリしてしまうなど明らかに様子が変化します。
人にとっては少々肌寒いかもしれませんが、できるだけその気温を維持するようにしてください。
(エアコンを常時つけっぱなしが厳しいようなら冷却器や扇風機などでの代用方法もあります)
もしそれ以上の温度でぐったり倒れていたら室内を冷やすか、より涼しい場所に移動して水を与えましょう。
もしここで水を飲めないほどぐったりしているようなら動物病院に電話をしましょう。
電話口で応急処置の仕方だけでも教えてくれます。
特に夏場などは熱中症で命を落とすうさぎが少なくありません。
室内の温度には充分に気を配って飼うようにしてください。
歩行異常
本来うさぎは外敵から身を守るために俊敏に動き回る動物です。
そのため、歩行がおかしいというのは異常な状態であると考えられます。
理由は上にもあげた皮膚炎や外傷、もしくは骨折や神経症の疑いがあります。
歩き方や動きがおかしかったら迷わずに病院へ連れていきましょう。
あまり動かせずに安静にすることが望ましいです。
怖がらせたり脅かしたりすると、うさぎはその場から全力で逃げようとします。
かなりのスピードなので打ち所が悪いと骨折や脱臼の危険性が有ります。
うさぎは臆病な動物なので不必要な脅かしなどは絶対にしてはいけません。
また、うさぎの大半はよほど慣れていない限り抱っこされるのを嫌います。
立ったまま抱きかかえて、そこからうさぎが逃げるように落下してしまうと大変危険なことになるため、やめましょう。
もし抱きかかえたい場合はきちんと座りながらゆっくりと行ってください。
ケージに広い隙間が有ったり爪が伸びていたりする場合も注意が必要です。
抜こうと暴れる際に骨折してしまうことがあります。
事故を防ぐため、できるだけ挟まってしまうようなスペースは周囲に作らないことが大切です。
神経症状
うさぎがずっと首を傾けている、目が左右に動き続けている、床の上で転がりまわっている、痙攣する、またまっすぐ歩けないなどの症状がみられた場合は神経症状が疑われます。
こうした神経症状が出る原因として、主に細菌感染か寄生虫による脳炎、中耳炎、また内耳炎があがります。
それ以外だと遺伝で起きる先天性疾患、栄養失調、また中毒などです。
できれば8時間以内の診療が望ましいです。
人もそうですが、神経というのは時間が経てばたつほど回復が遅くなり、治療をしても後遺症が残ってしまう可能性があります。
早期治療が決め手になります。
尿石症
尿路結石症とも呼ばれています。
尿に含まれるリン、カルシウム、そしてマグネシウムが結晶化して結石となる病気です。
尿が排出できなくなることから尿毒症になってしまったり、生命に関わる病気にも発展する可能性があるため、早急に医療機関で治療する必要があります。
症状としては、食欲不振、血尿、発熱のほか、排尿時の痛みのために背中を丸めてうずくまったりします。
干し草やペレットなど乾燥食物を食べているうさぎにはできるだけきれいな水をたくさん与えてあげましょう。
水分の多い野菜などでも効果的です。
またカルシウムを多く含むペレットやパンなども結石が出やすくなるといわれています。
長期に渡って与えるのは避けましょう。
また、細菌感染も考えられるので、ケージやトイレは清掃して衛生状態を保つこと。
糖尿病
インスリンの分泌が鈍り、高血糖になってしまうことで起こります。
肥満のウサギには、初期症状として多飲多尿が多くみられます。
進行すると血管や内皮細胞を破壊していき、人間のそれと同じく様々な合併症が出てきます。
重症化すると手術になってしまい、お金も手間も大幅にかかってしまう恐れがあります。
飼い主としてはおやつなどをついあげてしまいがちですが、毎回ではなくたまにご褒美としてあげるくらいで留めておきましょう。
肥満が糖尿病の引き金になることが多いので、食事の量も日ごろから注意する必要があるでしょう。
うさぎが大人になってもアルファルファのペレットを中心に与えている方がいますが、こうした食事は肥満になりやすいので、すこしずつティモシー牧草に切り替えて健康的な食事を習慣化させることです。
また、桑の葉は糖の吸収を抑える効果があるので、配合されているペレットを選ぶのもよいでしょうね。
参照サイト:ウサギの病気いろいろ | きりがおか動物病院(神奈川県横浜市) フェレット、ウサギ、ハムスター
症状がでたらすぐに対処を
明らかに歩き方がおかしかったり、食欲や元気が無かったりした場合は何か原因があると思った方がよいでしょう。
もちろん動物なので一時的なコンディションであることも多いのですが、予防しておくに越したことはありません。
正しい生活習慣だけでなく、病気の種類や応急処置の仕方などの知識を一通り得ておきましょう。
症状や対応の仕方がわからない場合、くれぐれも独断で勝手に判断したりはせず、水分をあげたり体を温めるなどできるだけ安静にさせてください。
うさぎを診る病院は未だ少数
うさぎを含むエキゾチックアニマルを上手に診られる病院はまだ非常に少ないのが現状です。
うさぎの体のことをよく知っている獣医は実はまだそれほど多くなく、誤診や麻酔などで命を落としてしまうことも珍しくありません。
うさぎにはウサギ特有の病気も多く、場合によっては専門的な治療を施せる医療機関ではないと手遅れになる場合が多々あります。
また、うさぎは自分の具合が悪いことを人前で隠す癖があります。
捕食動物なので、外敵に自分が弱っていることを隠す習性があり、これは飼い主の前であっても例外ではありません。
そのため、弱っているのが目で見てわかったときには相当症状が進んでいることがあるのです。
こうした理由もうさぎの病気を見落としてしまう原因になっています。
うさぎを家にお迎えする前に、できる限り病気をしないように健康管理に気を配りつつ、大事に育てることを誓うと同時に、「専門病院が近くにあるか」や「上手に診てくれる獣医さんはいるのか」を必ずチェックしておくことが大切です。
うさぎを診ることができる動物病院一覧
東京都にあるおすすめのクリニックです。
急な異変にも対応可能な病院があります。
動物の病気について様々な相談ができます。
詳しくはHPよりお問い合わせください。
草創舎動物病院
東京都小平市学園西町2-11-33
つばめ動物病院
東京都品川区中延6-9-7-1F
うさぎのびょういん joyjoy
東京都国立市北1-4-1 国立北Kビル101
すみれペットクリニック
東京都立川市一番町2-33-12 ラディーナマンション102
世田谷通り動物病院
東京都世田谷区世田谷1-14-20
あだち動物病院
東京都昭島市中神町1377-3
まとめ~普段から予防を心掛けよう
いわずもがな、飼育中のうさぎが病気に罹らないようにするには何よりも普段からの予防が重要です。
以下の習慣を守ることがうさぎの健康寿命を延ばすことに繋がります。
- 成長段階に応じて与えるご飯の内容を変えていく
- 最低でも3日に1度はケージ内やトイレの清掃をする
- 食事量や運動量に関する情報やアドバイスはしっかり聞いておくこと
- 肥満にさせないこと
- うさぎを上手に診ることができる獣医をさがしておくこと
- ウサギの生態、病気の種類、また負傷の際の応急処置の知識を身に付けておくこと