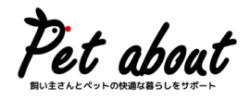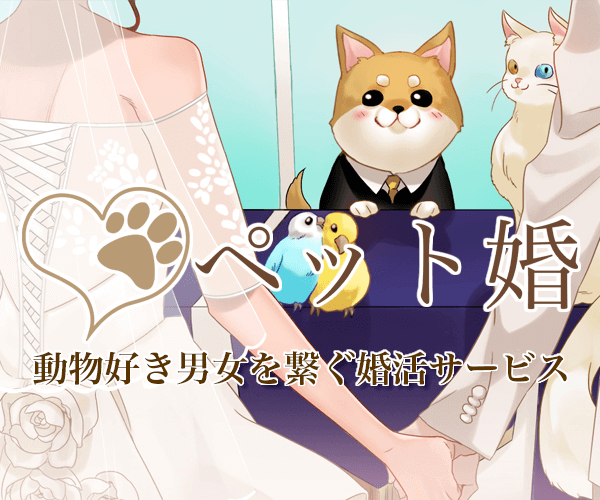フェレットの平均寿命は6~8歳ほどと言われており、生まれてからの成長が早く、4歳の時点でシニアと言われています。
年に1度の定期検診や感染症のワクチンを受けることで予防できる病気もあれば、早期発見、早期治療を行うことで重篤化を防げる病気もあります。
少しでも健康で長生きしてもらうためにフェレットのかかりやすい病気や症状、予防法などを覚えておきましょう。
フェレットがかかりやすい病気とは
フェレットはとても人に懐きやすく、近年ペットとして人気のある動物ですが、実はとても病気にかかりやすいと言われています。
フェレットはフェレットを飼い始める前に、フェレットを診ることができる動物病院を探しておくことも大切です。
さっそくですが、フェレットのかかりやすい病気やその症状とは、またその予防法や対策を紹介していきます。
フェレットの3大疾病
フェレットは感染症や白内障、歯肉炎など様々な病気にかかる可能性がありますが、その中でもかかりやすいものとして三大疾病と言われる3つの病気があります。
それはインスリノーマ、副腎疾患、リンパ腫だと言われています。
それぞれ、どんな病気なのか、その症状と治療法、予防方法などを見ていきましょう。
インスリノーマ(低血糖)
インスリノーマは膵臓の腫瘍で中~高齢のフェレットによく見られます。
膵臓から分泌されるインスリンはホルモンの1種で、血液中の糖分のを体の細胞に取り込ませる働きがありますが、インスリノーマのフェレットは腫瘍化した膵臓の細胞からインスリンが多量に分泌します。
多量に分泌されることにより、血糖値が低下し様々な症状を引き起こします。
| 症状 | 初期の症状は寝ている時間が長い、ぼんやりしているなど気づきにくいものが多いため気づかないうちに進行していることもあります。 ヨダレが出る、前足で口元をこすったりする、後ろ足に力が入らずぐらついている、震えている、失禁するなどの症状が現れます。 ひどくなると意識を失ったり、昏睡状態に陥ったり、痙攣を起こすこともあります。 |
|---|---|
| 治療 | インスリノーマは外科治療と内科治療があります。 外科治療の場合、腫瘍を摘出してインスリンの量を減らし、インスリノーマの症状を軽減します。 内科治療はステロイド剤などの投与で血糖値を上昇させ低血糖を防いだり、高タンパク食などを用いた食事療法を行います。 |
| 予防 | 確実な予防法はありませんが、毎日の食事や栄養が予防につながる可能性があります。 炭水化物の多い食事は避け、良質で高たんぱくな食事を与えるように心がけましょう。 |
副腎腫瘍
副腎腫瘍はフェレットの副腎腫瘍から分泌される性ホルモンが過剰に分泌して起こる病気です。
副腎は、腎臓の近くにある小さな2つの臓器で、腫瘍化や肥大化することで発症します。
日本で飼われているフェレットのほとんどは去勢、避妊手術をしているため、ホルモンを分泌させる臓器があります。
そのため、行き場がなくなったホルモン成分は副腎の性ホルモン分泌組織に作用してしまいます。
| 症状 | 副腎疾患のは尻尾から始まり、お尻、脇腹などに左右対称の脱毛が見られます。 副腎腫瘍に罹患したフェレットの90%に脱毛が発生すると言われています。正確には発毛不全により、換毛期の際に古い毛が抜け落ち、本来はそれと同時に新しい毛が発毛しますが、新しい発毛が起こらず地肌が露になる状態です。また、オスは前立腺肥大により尿が出にくくなり、メスは陰部の肥大が見られることが多くなります。 |
|---|---|
| 治療 | 外科手術にて腫瘍を摘出する場合や、投薬治療による内科治療があります。 投薬治療をする場合は、ホルモンの過剰分泌を抑える薬を使用します。 |
| 予防 | 残念ながら副腎腫瘍の完全な予防法は確率されていません。 ですが、早期発見、早期治療が重要となりますので、定期的に検診を受けるようにしましょう。 |
リンパ腫
リンパ腫は、血液中にある白血球の1つであるリンパ球がガン化する血液のガンの1種で、高齢のフェレットによくみられる病気です。
リンパ腫は特定の部位に起こる病気ではなく、全身至るところで発生する可能性のある病気で、兆候を読み取るのが難しい病気と言われています。
| 症状 | リンパ腫に侵されたリンパ節は腫大しますが、リンパ節の部位により症状が異なります。 |
|---|---|
| 治療 | リンパ腫は完治できない病気ですが、抗癌剤治療により延命が期待できます。 ですが、抗癌剤治療は腫瘍の状態により治療間隔を伸ばすことはできますが、治療そのものは一生つづくことになります。 |
| 予防 | リンパ腫の発症の原因が不明なため、発症自体を予防することは困難ですが、早期に発見することによりガンが進行する前の治療が可能です。 |
感染症
フェレットも犬や猫、そして人間のように感染症にかかることがあります。
フィラリア
フィラリアという線虫の寄生によって起こる病気で、犬の病気としてよく知られています。
フィラリア症は感染した動物の血液を吸った蚊にさされることにより感染します。
フィラリアの幼虫はフェレットの体内で成長し、3~4ヶ月ほどかけて心臓まで移動し、心臓に寄生して心不全の原因となります。
| 症状 | 咳、食欲不振、腹水、元気がないなどの症状が見られます。 幼虫が血管や心臓の血液の流れを塞ぎ、突然死を起こすこともあります。 |
|---|---|
| 予防 | フィラリアの予防薬を用います。 蚊が出始めた頃からいなくなって1ヶ月後まで月に1回投薬します。この薬の効果は、蚊を媒介に体内に入ってきたフィラリアの幼虫を殺す作用があります。 |
ジステンパー
ジステンパーは犬の感染症の1つですが、フェレットも感染します。
体の小さなフェレットが感染した場合の致死率はほぼ100%となっており、ジステンパーに有効な治療法はありません。
| 症状 | 約7日ほどの潜伏期間を経た後、食欲不振、目ヤニ、鼻水、口周りの発疹などの症状が見られます。 |
|---|---|
| 予防 | 日本にはフェレット専用のジステンパーワクチンはありませんが、犬ジステンパーに使用されるワクチンを打つことによりジステンパーの抗体をつくります。 接種時期は生後1年以内は2~3回を間隔を空けて接種し、その後は1年おきに接種するようにしましょう。 またペットショップなどでジステンパーに感染した動物などを触り家のフェレットに感染させてしまうこともあるため、動物と接触したあとは手を洗い消毒するようにしましょう。 |
インフルエンザ
フェレットは人間から感染したり、人間へ移したりする病気があります。
人間にとっては身近な風邪やインフルエンザも該当します。
| 症状 | 目ヤニや鼻水、咳やくしゃみ、食欲不振、発熱、下痢などが見られます。 |
|---|---|
| 対策 | 飼い主である人間がインフルエンザに感染した場合には、フェレットにも移してしまう可能性があるため感染させないように注意するようにしましょう。 また多頭飼いをしている場合は、フェレット同士の感染もあるため、感染したフェレットは別の部屋やケージなどで隔離して治療してあげてください。 |
まとめ
フェレットに多い病気をまとめてみました。
フェレットは病気になりやすく、一生に1度は大きな病気にかかると言われています。
そのため日頃からのケアや定期的な健康診断が不可欠です。
早期に病気を発見し治療することで、治療期間やフェレットの負担も大きく軽減されます。
また、普段の食事やフェレットの過ごす環境を良くすることで病気の予防や対策にもなります。
普段からフェレットの体重や食欲、また排泄物などを確認するようにし、少しでも異変を感じた場合は情報を鵜呑みにしたり自己判断せず、動物病院へ連れて行くようにしましょう。